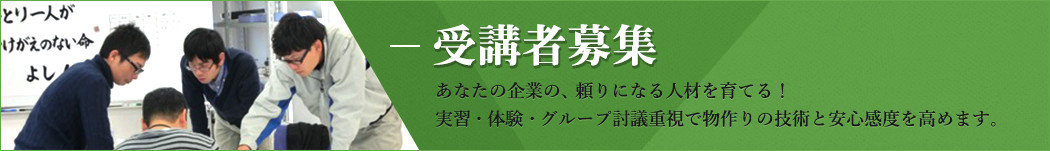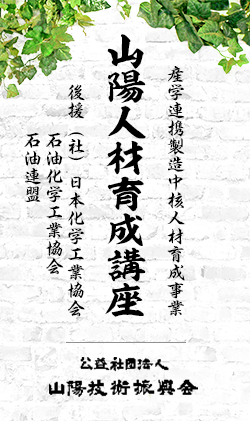講義詳細
技術力強化コース(2024年度)
設備材料の損傷と管理(リモート)
この講義はリモート講義です
お申し込みの受付を終了致しました。
| 日時 |
|
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 場所 | 地図はこちら |
| 料金 | 24,200円(税込み) |
概要1
科目概要:
1970~1980年代に建設された石油化学をはじめとするプラント群は、40~50年を経過してなお現役として稼働しており、経年化による設備材料の損傷とその管理は重要課題となっている。高温・高圧・腐食環境の過酷な条件で多量の危険物を取扱い、コスト低減と生産性向上が生き残りのための必須事項で、長期連続運転を実施している装置産業では事故防止が最優先事項となっている。そこで本科目では、「設備材料の損傷と管理」をテーマに、主に設備管理・運転管理を生業とする若手技術者と管理者を対象に、体系的な管理とそのために必要な基礎知識を研修できる講座を目指して、基本的な知識と技術を提供、事例を中心にした研修で事故防止の管理を可能とする技術者の育成を目指す。
研修目標(科目全般)
1.目標の方向:設備材料の損傷に関する基礎知識と体系的な管理の方法を提供し、事故防止の管理を可能とする技術者と管理者(スキル度ランク3)の育成を目指す。
2.レベルアップの目標:スキル度(*) ランク2→ランク3
(*)ランク 0 設備材料の損傷の基礎知識と管理の技術はない
〃 1 〃 〃 は多少ある
〃 2 〃 〃 はある程度ある
〃 3 〃 〃 はかなりある
〃 4 〃 〃 は指導できる
3.材料の損傷に関わる基礎知識と管理のための技術の習得とその必要資料を準備する。
対象とする研修参加者
化学や石油化学などのプラント設備の損傷とその管理の技術習得を目指す若手技術者と管理者
(1)主対象者:化学や石油化学などのプラント設備の運転、設備管理に従事する技術者
(2)その他の対象者:(1)の他、プラント設備の設計、建設、運転、設備管理などに関わる業務に従事する技術者や建設工事会社の技術者
当科目の特徴
本講座では静装置材料を中心とした経年化に伴う劣化損傷の知識と、それをどのように管理すれば良いのかについて、講師の長年の経験に基づく管理方法(原因特定・優先順の設定・診断評価・措置対策・予防等)の事例を交えて講義・演習を進めます。
1.静装置の設備材料の損傷を中心に、腐食・摩耗・エロージョン・脆化などの劣化モードごとにメカニズムなどの一般的な基礎知識を学ぶとともに、そこからトラブルや事故を防止する管理の方法や技術を身に付ける。
2.設備材料の損傷の事例を基に実際に適用された具体的な管理の技術と方法を学ぶことで、劣化防止の運転管理や管理に関わる検査技術・診断技術などの周辺技術を習得する。
3.高経年化設備の管理、特に外面腐食や配管の管理、SUS304製機器の鋭敏化、塗装、熱交換器鋼管の冷却水による腐食などの個別損傷の管理の実例をまとめて学ぶことで、適切な管理の方法を構築できる能力を養う。
研修に必要な期間:受講期間1日間:90分×4コマ+質疑 9:00~16:30
受講生数:20名
講師:林 和弘(工学博士、元三菱化学(株)フェロー・設備技術部、元三菱化学エンジニアリング(株) 設備管理事業部長、日本プラントメンテナンス協会 上席主幹研究員、 安全・安心科学研究所 アドバイザー、化学工学会 SCE-net会員)
研修方法と事前準備:座学と事前準備(テキスト内の書式に記入)を利用した演習討議
概要2
コマ1:設備材料の損傷と管理の概論
研修目標:高経年化設備を抱える現代の大きな課題の設備材料の損傷と管理の概観を知る。
① 事故統計などから高経年化設備、特に材料の損傷と管理が課題であることを知る。
② 損傷の種類や概要を減肉・割れ・変質などの劣化現象と劣化モードの分類などで学ぶ。
③ 設備の劣化を基点とした管理の方法についての概要を学ぶ。
従来と比較した新規性:設備材料の損傷の概観を知って、本講座の背景となるトラブルや事故防止を図る管理の必要を認識する。次に高経年化設備の管理の技術として劣化を基点とした管理の方法を学ぶ。
コマ2:設備材料の一般的な損傷と劣化モード
研修目標:設備材料の一般的な損傷について個別の劣化モードごとに知識を得る。
① 腐食・摩耗・エロージョン・脆化などの劣化モードごとの劣化形態や劣化メカニズムを学ぶ。
② 損傷の一般的な基礎知識を学ぶことでトラブルや事故を防止する管理の方法や技術を身に付ける。
従来と比較した新規性:静装置設備の損傷を中心としているが劣化モードごとの知識をまとめて得ることでトラブルや事故を防止する運転・設備管理に必要な関連技術が理解できる。講義内容から検討テーマの設定、および回答を募り討議する。
コマ3:設備材料の損傷と管理に関わる周辺技術
研修目標:材料の基礎知識や損傷の検査や診断評価に必要な診断技術などの周辺技術を知る。
① 設備材料に使用される材料の分類や種類とその用途、損傷劣化に影響する性質などを知る。
② 損傷劣化の現象を把握・評価するための非破壊検査や一部サンプリングなどの破壊検査の方法や技術、その他診断技術の種類や特徴・注意点など概要を知る。
従来と比較した新規性:設計・建設・運転・設備管理に必要な静装置設備に使用される材料の基礎知識、および損傷劣化の現象を把握・評価する検査・診断・評価技術をまとめて得ることで適切な材料選定や診断技術を適用する能力を向上する。講義内容から演習問題を策定、回答を募り討議する。
コマ4:設備材料の損傷と劣化の管理の適用事例
研修目標:設備材料の損傷を含む劣化と管理について個別の標準化した技術の適用事例を学ぶ。
本講座の必須は①から④で、⑤以降は参考とし資料の提供のみとしている。
① 配管の劣化の管理
② 外面腐食による劣化の管理
③ 塗装の劣化の管理
④ ステンレス機器の鋭敏化による劣化の管理
⑤ 熱交換器鋼管の冷却水による腐食劣化の管理
⑥ 高温水素による損傷劣化の管理
⑦ CO-CO2-H2OによるSCC劣化の管理
従来と比較した新規性:現代の大きな課題となっている設備材料の損傷と管理について個別の標準化した技術を適用事例で学ぶ。質疑応答で理解を深める。
この講義はリモート講義です
お申し込みの受付を終了致しました。