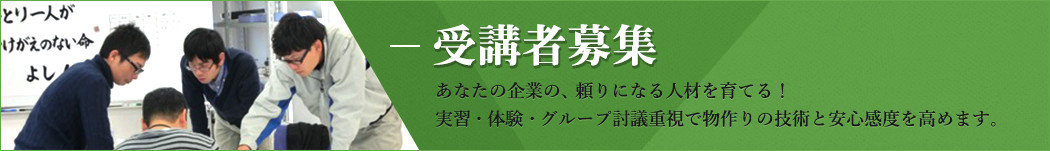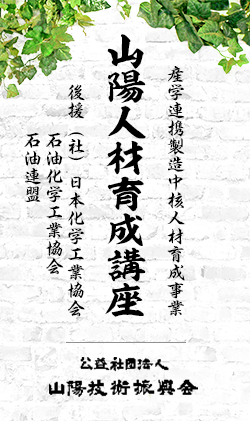講義詳細
技術力強化コース(2024年度)
反応工学(リモート)
WEB受講の場合の昼食は用意されません。
お申し込みの受付を終了致しました。
| 日時 |
|
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 場所 | 地図はこちら |
| 料金 | 48,400円(税込み) |
概要1
科目概要:反応器の「設計方程式」を学習し 最適な反応器の選定法を修得。「非等温型反応器」を学習し 反応器に限らず 化学物質を扱う全ての機器に共通な反応リスクと安定操作の閾値を理解する。
研修目標:製造業務に必要な反応工学の基礎知識を修得し、業務の幅を広げるとともに、現場での安定・安全運転操作の閾値を理解するとこで、プロセスを管理する能力の向上を目的とする。また開発業務においては最適な反応器の選定やスケールアップの基礎を修得することを目的とする。
対象とする研修参加者: 設備の運転従事者(オペレーターなど)、設備の保全従事者(保全技術者など)、研究開発に従事しステージアップ業務に関わる者
科目の特徴: 従来の反応工学は反応器の設計者を対象としており、製造現場の運転者や研究開発担当者向けではなかった。この講座では、最適な反応器の選定やスケールアップの考え方を提供するとともに、現場の安全・安定運転管理に役立ち、現場の条件変更に潜む危険を定量的に気づけるよう配慮した内容としている。また、電卓を用い基本的な例題や演習問題を扱うことで基本的考え方を理解し、問題の解決を基礎から行う方法が修得できる。ポイントの説明、例題の解説、演習の実施と解説、テストと繰り返し学習することで、理解を確実なものにする。履修者は「APT(運転体験 )」を受講すると良い。更にプロセス開発、改良、設計を学びたい方は「化学工学基礎」および「化学工学通論」を受講すること。
研修に必要な期間:1コマ当たり受講期間: 60分~180分。全時限数 12時間 (二 日間) + 70 分テスト。9:00~17:00
受講生数:20名
ティーチング・メソッド:座学と演習
講師:青木 肇也(山陽技術振興会、元旭化成)
概要2
コマ1-1,2:反応工学の基礎(1)(60分+事例解説と演習20分)第一日 9:00~
反応工学は、①反応速度式や②物質収支を定量的に扱い、最適な反応器(反応形式・大きさ)を計算しスケールアップを橋渡しする技術である。更に、化学反応の③熱・エネルギー収支(熱力学)や④反応温度依存性(アレニウスの式)を定量的に扱う技術として、プラントの安定・安全運転や生産管理における反応工学の役割を学ぶ。
コマ1-3,4:反応工学の基礎(2)(40分+事例解説と演習40分)第一日10:30~
反応率やモル濃度など基礎的な反応工学の単位や、反応式から導かれる量論式に対応する速度式の考えを理解した上で、反応次数への展開を通して反応工学の基礎的な概念を学習する。
コマ1-5,6:反応工学の基礎(3)(40分+事例解説と演習20分)第一日12:50~
反応工学の基礎的な概念を反応次数の求め方や可逆反応へ拡張し平衡反応を学習する。
コマ2:回分型反応器(30分+演習20分) 第一日14:00~
最初に、回分型反応器の実例を紹介する。物質収支に着目すると、反応速度式に応じた設計方程式が導かれることを学習する。演習を通して理解を深める。回分型反応器は反応時間に加えて仕込み・回収等の操作時間も考慮しなければならないことも学習する
コマ3:連続槽型反応器 (30分+演習20分)第一日15:00~
次に、連続槽型反応器の実例を紹介する。基礎的な物質収支の考え方を学ぶ。物質収支に着目すると、反応率と平均滞留時間から簡単な設計方程式が導かれることを学習する。演習を通して理解を深める。補足として、連続2槽型反応器への拡張を学習する。
コマ4:管型反応器 (30分+演習20分) 第一日16:00~16:50
管型反応器の実例を紹介する。物質収支に着目すると、平均滞留時間に応じた設計方程式が導かれることを学習する。演習を通して理解を深める。回分型反応器、連続槽型反応器、と管型反応器の違いを比較し理解を深める。
コマ5:反応器サイズと滞留時間(復習10分+30分+演習10分)第二日 9:00~
連続槽型反応器と管型反応器の体積の優劣は反応速度式に依存することを学習する。連続槽型反応器を無限に繋げると管型反応器と同等になることを確認する。補足として滞留時間の測定法と滞留時間分布について知識を深める。
コマ6:酵素反応(触媒反応) (30分+演習20分) 第二日10:00~
複合反応の例として酵素触媒反応の速度式を学習する。更に演習を通して理解を深める。補足として、酵素触媒反応の解析法を学習する。こうした解析が触媒反応一般に適用できることを理解する。
コマ7-1:反応熱 (30分+演習20分) 第二日11:00~
化学反応に伴い熱の移動があり反応温度が変化する。そこで基礎的な反応熱とエネルギーの関係式(熱力学第一法則)や反応熱の計算方法を学習する。演習を通して理解を深める。更に、簡単な反応熱の推算方法を学習する。
コマ7-2:アレニウスの式 (40分+演習10分) 第二日12:50~
反応温度の温度依存性を表すアレニウスの式と活性化エネルギーを学習する。アレニウスプロットから実験的に活性化エネルギーが導けることを学習し、演習を通して理解を深める
コマ8:非等温反応の安定操作(40分+演習と応用例30分) 第二日13:50~
実際の反応器の内温は一定ではなく僅かな時間変動をしている。連続槽型反応器の熱収支から除熱量と発熱量の関係式を求め、温度変動には安定領域と不安定領域があることを学習する。最後に、演習の中で、ある異常反応の発熱と除熱の関係図を見ながら、なぜ安全な保存タンクが危険な暴走反応器に変貌したかを確認する。こうした実例から、実際のプラント操作におけるリスクを反応工学の視点で解析し安全運転の基本条件を理解する。
テストと解答:(70分+10分) 第二日15:10~16:30
アンケート記入、終了証授与:第二日16:30~16:50
WEB受講の場合の昼食は用意されません。
お申し込みの受付を終了致しました。