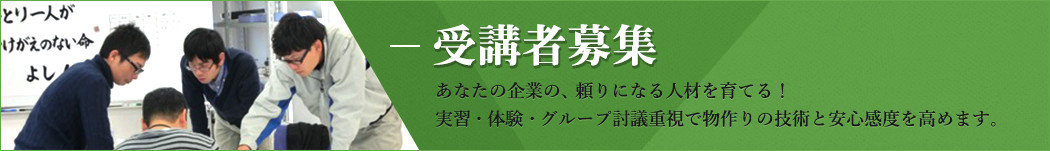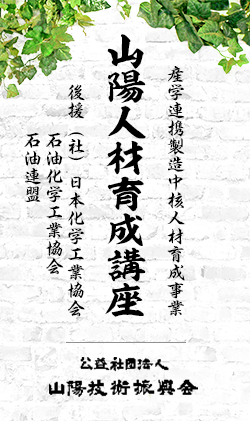講義詳細
リスクマネジメントコース(2025年度)
事例から学ぶ労働災害対策
| 日時 |
|
|---|---|
| 定員 | 20名 |
| 場所 | 水江研修室 倉敷水江170番地 地図はこちら |
| 料金 | 48,400円(税込み) |
概要1
科目概要:
全産業の労働死傷災害の事故型別分類では転倒、墜落・転落、挟まれ・巻き込まれの 順に多いが、製造業に限ると機械への挟まれ・巻き込まれ型が最も多く、死傷者数では24%、死亡者数では 40%を占めている。また、化学薬品による薬傷、工事時の感電事故、酸素欠乏空気による酸欠死亡事故もしばしば発生している。
これらの労働災害防止の為に、各社では職場に労働安全に関する有資格取得者を配置すると共に、各種のマネージメントシステムの導入・機械安全規格の活用など労災防止に努めている。しかし、「人の特性」によりこれらの構築したシステム・規格などに「隙間」が生じ労働災害が発生している。
本講座では、労災の実例を通じて、人の特性により生じた「隙間」を考え、受講者とともに災害の要因・対策を討議する。
研修目標:
労災事例の検討を通じて労災の原因となる様々なシステムの「隙間」を学び、労災を起こさない、起こさせないことでより安全な職場にするための能力を向上させる。
対象とする研修参加者:
部品加工・樹脂加工・フィルム製造などで自動設備・プレス機などを使用する職場、化学・石油・発電などの職場の作業者・安全担当者
科目の特徴:
それぞれの職場では、労働災害を防止するために様々なシステムを取り入れ、設備的な対応も図っているが、それらの「隙間」から労災が発生している。
職場で起きている具体的な様々な労働災害事例を人の特性に着目して、ⅰ)主として人の行動に起因するタイプ(行動系労働災害)、ⅱ)主として設備に起因するタイプ(プロセス系労働災害)に分けて説明し、人の特性と災害の関連について考える機会を提供する。また、実際に起きた事例について事故原因、要因、対策についてグループ討議・発表・質疑応答を行う参加型の研修を行う。
収得に必要な期間:2日間(9:00~16:30)
1日目はコマ1~コマ4について昼食、休憩をはさみながら講義を行い、コマ5にてグループ討議・発表・質疑応答を行う。
2日目は1日目と同様にコマ6~コマ9について講義を行い、コマ10にてグループ討議・発表・質疑応答を行う。
受講生数:20名
ティーチング・メソッド:座学とグループ討議・発表
本講座では、初めに労働災害防止のための考え方・システム・規格・人の特性、実際の職場で起きている様々な労災事例の説明とグループ討議・発表・質疑応答を組み合わせた討議・発表型の講義を行う。
講師:元石油化学工業協会技術部長 岩間啓一
概要2
第1日目
コマ1:労働災害防止のための取り組み
労働災害防止のための考え方、施策について説明を行う。
(1) 労働安全の歴史と現状
(2) 労働災害の原因、防止対策の考え方~機械安全、人の特性~
コマ2:行動系労働災害-転倒-
転倒災害は日常生活の中でも起きており、対策の難しい災害の一つである。本コマでは床、階段などでの転倒に関する労災事例を説明したあと、コマ2(転倒災害)のまとめについてグループ討議を行い、事故防止を考える機会を提供する。
コマ3:行動系労働災害-墜落・転落-
墜落・転落災害は死亡などの重篤な災害となる場合が多い。本コマでは墜落・転落に関する労災事例を説明したあと、コマ3(墜落・転落災害)のまとめについてグループ討議を行い、事故防止を考える機会を提供する。
コマ4:行動系労働災害-挟まれ・巻き込まれ-
製造業で最も多く発生している労災が挟まれ・巻き込まれ災害であり、四肢の欠損、死亡事故となることが多い。本コマでは機器ごとに特徴的な挟まれ・巻き込まれ労災事故を説明する。
コマ5:グループ討議(1)
講師が提供するコマ2~コマ4に関する労災事例についてグループ討議を行い、事故の要因、対策の検討を行い、発表、質疑応答を行う。
第2日目
コマ6:行動系労働災害-挟まれ・巻き込まれー (続き)
第1日目に引き続き、挟まれ・巻き込まれ労災事例説明の続きを行ったあと、第1日目の事例もあわせてコマ6(挟まれ・巻き込まれ災害)のまとめについてグループ討議を行い、事故防止を考える機会を提供する。
コマ7:プロセス系労働災害-薬傷・火傷-
プロセス系労災の代表事例である薬傷・火傷に関する労災事例を説明したあと、コマ7(薬傷・火傷災害)のまとめについてグループ討議を行い、事故防止を考える機会を提供する。
コマ8:プロセス系労働災害-酸欠-
酸欠防止に関する知識は広く普及しているが、それでもしばしば酸欠死亡事故が発生している。本コマでは酸欠に関する労災事例を説明したあと、コマ8(酸欠災害)のまとめについてグループ討議を行い、事故防止を考える機会を提供する。
コマ9:プロセス系労働災害-感電-
高圧電源のみならず、低圧電源においても感電事故が起きている。本コマでは感電に関する労災事例を説明したあと、コマ9(感電災害)のまとめについてグループ討議を行い、事故防止を考える機会を提供する。
コマ10:グループ討議(2)
講師が提供するコマ6~コマ9に関する労災事例についてグループ討議にて、事故の要因、対策の検討を行い、発表、質疑応答を行う。
参考図書
① 黒田 勲「信じられないミス」はなぜ起こる―ヒューマン・ファクターの分析(中災防新書)
② 丹羽三千雄安全はトップの生き方―安全確保は義務である―(中災防新書)
③ 芳賀 繁 失敗のメカニズム
④ 厚生労働省リスクアセスメント等関連資料(教材一覧)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14
⑤ 向殿政男よくわかるリスクアセスメント-グローバルスタンダードの安全を構築する(中災防ブックス)
⑥ 中野洋一なくそう!墜落・転落・転倒(中央労働災害防止協会)
⑦ 中村昌允製造現場の事故を防ぐ安全工学の考え方と実践(オーム社)
⑧ 厚生労働省事例でわかる職場のリスクアセスメント(2007)
⑨ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、プロセスプラントのプロセス災害防止のためのリスクアセスメント等の進め方JNIOSH-TD-NO.5(2016)
⑩ 土屋正春機械安全分野の安全規格の体系化.安全工学.Vol45 No.5(2006)
⑪ 中央労働災害防止協会.機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック(2015)
⑫ 製造業安全対策官民協議会、
労働災害につながる具体的手法として~「意図的なルール違反・ヒューマンエラーを リスクアセスメントに反映させる共通的な手法」を開発(PRESS RELEASE資料2019)