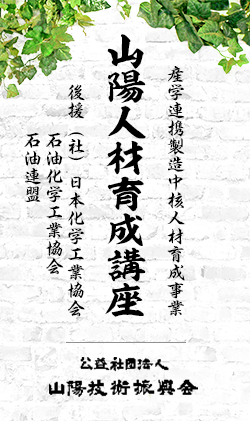受講者の声
- TOP
- 受講者の声
安全・安定運転基礎コース(2023年度)
- 設備管理3日間コース(対面のみ)
- 設備管理2日間コース(対面のみ)
- 化学工学基礎
- 安全体験Aコース(対面のみ)
- 安全体験Cコース(対面のみ)
- 安全体験Dコース(対面のみ)
- 原因究明力開発
- トラブル事例分析による事故災害の未然防止
- 現場の化学
- 計装基礎(対面のみ)
設備管理3日間コース(対面のみ)
今回、①自分の理解度の確認、②生産オペ向けの自主保全活動の教育に対して有効な資料や理解し易い説明の勉強、のため参加させて頂きました。
①については、電気関係の無知さを再確認。なかなか普段使わない事は覚えない、理解出来て無いですね。精進します。
②は、本資料はそもそも旭化成のオペ1年目教育に使用しているとの話もあり、非常に分かり易いものとなっていました。また、対保全員に向けても、保全はOJT指導が多く誤った理屈で教育されていることもあるため、その変もしっかりとした理屈の上で学べる様な講習であったと感じます。
あと、1年2年目で受けるのも良いが実務経験を経て7.8年後くらいに受講するのも、また当時とは違った視点で見えて良かったです。
保全の分野が多く、個人的に難しいと感じる部分が多かったが、1年会社で働き現場を知っていたので理解できた部分が多いと感じた。また、自身の所属する電装関係の講義もありなんとなく知っていただけ部分の理解が深まったため非常に有意義な講義だった。制御、腐食、バル、計装の講義は実際に実務で活かすだけでなく、後輩などができた際の教育に活かしていきたいと思う。
普段の仕事の中でなかなか構造をしれない(分解できない)ところまで見させてもらい、この3日間でかなりの知識を得ることが出来た。社内でトラブル時の対応や仕組みを後輩に説明する際も、この知識を活かして提案や、教育ができるよう努めていきたい
全体を通して基本的な部分から学ぶことができ有意義な時間となった。知らなかった知識については復習し今後の業務に役立てていけるようにしたいと思う。また、計装や電気、設備の診断に関する部分はまだ知識が足りていないと感じたので今後学びを深めていきたいと感じた。
設備管理2日間コース(対面のみ)
今回の講習で設備管理に付いて学んだが、今までなんとなく知っていたようなことも深く学べば奥が深いことに気が付きました。キャビテーションに関しては過去に自分の会社で全く同じことが起きており、当時この事を良く理解しておけば事前に対応して事故が起きていなかったかもしれないという思いになりました。今回学んだことは自分のスキルアップに繋げるのはもちろんですが、部下の教育にも役立てて行きたいと思います。今回の講習内容についてはベテラン、新人に関わらず知っておいた方がいいと思うので若手の方にもぜひ、行ってもらいたいと思います。
私の部署ではバルブ操作をする機会が多くある為、バルブそれぞれの特性、種類についての講義は大変有意義な時間となった。学んだ知識は自分のものだけにするのではなく、私のような若手社員や新人社員に伝えていきたい。またその時は今日の講義資料と共に現場で現物を見て教えたいと思う。講義資料は職場で回覧して内容を周知したい。
化学工学基礎
設備設計で化学工学を学ぶことは非常に重要で、本部署には必須と感じました。本日学んだことを設備設計などに活かしていきます。
レベルが高かった。予習しておいて良かったと思いました。関数付電卓の使い方から勉強する状態でしたので…。
浅い知識と経験と感覚で今までやってきた事もあり、勉強する機会を与えて頂き感謝します。復習することで理解を深め、資格取得を目指したいです。
アクションをする前に自前に計算し、大体の数値がわかるので計算してから実行するようにする。
プラント運転において感覚的・経験則によるものばかりだったが、更に今回の講習で学んだ知識をプラスしてより高度な運転・解析を実施していく。
自分の知らないことが多く、皆さんに付いて行くのが精一杯でしたが、専門的な知識だからと言って全く無知であるより何となくでも知っていたり、触れていることで仕組みや設備構造等、たくさん脳内で繋がった部分も多々ありましたので、とても大事なことだと改めて感じました。
3日間、教育ありがとうございました。
・高圧ガスの資格取得に役立つと思った。単位換算など基本単位に直す重要性を知った。
・自分の事業所でも計算してその装置が異常がないか調べてみたいと思った。
・化学基礎を学ぶ機会や製造工程にあまり関わることがないため、今回の講義は勉強になりました。特に担当しているエリアの製造プロセス方法の詳細を知ることができたので、今後現場では意識して見ていきたいと思います。
・基礎的な計算方法を資格取得面で活かしていきたいと思います。
安全体験Aコース(対面のみ)
火災、爆発、燃焼、高圧ガスは共通して大きな事故につながり、常日頃から気を付けていないと危険なので、この講座て学んだことをしっかり活用していきたいと思う。
・実際に燃焼、爆発の実験を見て改めて怖さが理解できた。今は定検で立ち合いをしているので、周りに可燃物がないか、TK内にガスがないかなどしっかり行おうと思う。
・現場にあるフレームアレスタの構造や用途を学べた。これからフレームテレスタの点検を行う時は金網に穴が空いていないかなどしっかり確認を行う。
普段の仕事の中で役に立つような講義内容でとても良かった。特に消火器などは普段めったに使うことがないため、こういう機会で勉強、復習しておいて、いざという時に適切な対応がとれるように準備していたい。
講義の中で最も印象に残ったのは製造所における火災着火原因の約4割が静電気によるのだということでした。私が業務中着用している作業服、安全靴は帯電防止用のものですが、靴底にごみが付着するなどして帯電防止性能が落ちることもあるため、こまめに靴底を確認しようと思いました。部署に1つは体が帯電していないかチェックするような装置を備えておく方が良いと思いました。
安全体験Cコース(対面のみ)
回転体は自社プラントでも多数存在するので、今回の講義内容から改めて危険行動の分析や安全多作等を上司と検討していきたい。高所作業はあまり多くないのですが、その分1回1回を注意して行おうと感じた。安全対策の成されていない場所はすぐに上司に報告し、対策について相談しようと思った。
今回の講義を通じて安全帯、フルハーネスで落下してしまった際の対応について知らなかったことが多くあったので、活かしていきたいと思いました。また保護器の点検等も今まで疎かになっていることが多いと感じました。社内に戻った際は再度見直したいと思いました。
安全体験Dコース(対面のみ)
共通して目には見えない潜在的な危険因子が題材でした。軽い気持ちで行った省略行為や怠慢が、災害や死亡事故に繫がることが良く分かった。あらゆる行動パターンに対応できる安全課が望ましいので、さまざまな視点を持って仕事に取り組みたいと思った。
電気技術者として電気事故は非常に身近な存在である。自分の判断ミスや知識不足が自身、他者の重大な電気事故につながってしまう恐れがある。それを防ぐためには適切な機器の選定(漏電事故対策だと漏電遮断器や個体接地)が重要であり、今回の講義を通してその重要性を学ぶことができた。今回学んだことを活かして安心、安全な設備を目指していきたいと思う。
・溶接作業中の逃走電流による感電・電気火災等を防止するため、アースは溶接母材に取り付けるよう、現場注意します。
・電気設備に近接した作業を行う際は、電気設備の絶縁状態を確保してから作業に着手します。
・現場において酸素濃度欠乏状態に気づくため、想像力を働かせたKYを行います。
原因究明力開発
この研修を受講して大変良い経験を得る事ができました。この技術を自部署に持ち帰り実作業SA時にロジックシンキングやケアビリティースタディを用いて潜在リスクの見える化に役立て、より多くのリスクを抽出して安全な職場環境を構築するために原因究明力が活かされると確信しました。
原因究明は現場でのトラブル解決に必須なので、今回の講座は非常に有意義だった一方で自身の知識レベルが工場しても、圧倒的に経験が足りていない現状を反省し、普段から意識して業務にあたる事が大事であると痛感した。特になぜなぜ分析は、入社からブ分部分では意識しているものの、まだ他の人から言われてからハッとする事が多々ある。今後は率先して自分が気づけるように意識して作業を心掛けたい。
今回の受講は原因究明力という事で、生産現場での作業においては、このスキルが非常に重要であると感じた。論理的な考え方や、多角的な見方で、起こった不具合やトラブルに対して真の原因を究明し、それを深掘りすることで有効な対策案が導き出せることを知った。今回学んだことを今後は自身の仕事に繋げていきたい。
保全担当として基礎的な知識・技能を学ぶ良い機会であった。名前こそ知らなかったものの、普段から何となく実施している技術もあり、点と点がようやく繋がった事柄もあった。今回学んだスキルは実務で繰り返し活用していき、確実に自分の物としていきたい。
トラブル解析では、トラブルが起こった時に、今回学んだなぜなぜ分析や、人や設備、システムの3つに分けて考えるなど、考え方を勉強したので、トラブル時に活かしていきたい。また、新入社員の教育を行っているが、教育で使用できそうな事もあったので合わせて活用していきたい 。
今回原因究明のやり方、目の付け所等グループ討議を通して学ぶことができました。私たちの職場はトラブルが多いので職場に帰ってからやり方を忘れる前に小さいトラブルでも解決し職場会社に貢献しようと思います。
今回の講義で学んだ5W1H、ツリー解析法、再発防止案は今後のトラブル防止・発生時のために積極的に活用していく。トラブルがなくても自職場の過去トラブル事例を使って実践していく。若手社員も増えてきているので、周りにも周知・教育していく。
自職場においては今後、設備トラブル等の原因究明が必要な事象が多くなる事が予想されます。
そこで、今回学んだ事として事実に基づくデータ収集や状況の整理を行い、経験則に頼り過ぎない事を心掛けていきたいです。
また、ゆくゆくは若手にも技術伝承をしていきたいと考えています。
上司の方にお願いしたい事は、上記を実行する上でのアドバイスをお願いしたいです。
普段の業務におきましても、チームで仕事を日々こなしていくため、問題が発生した場合には今回学んだKYマトリックス法や5W1Hは有効であるため、状況に応じ判断し使い分けていきたいと思います。また、グループ討議にて班長と書記を同時に行い、班員に意見を引き出しまとめる訓練も同時に鍛えられたので今回の研修で得た経験を業務にて発揮したいと思います。
発生しうる異常の早期発見・発生した場合の対応について事前に予知することで、異常の小さな内に対応できるということを再認識できた。
本研修で学んだ原因究明法を活用し、トラブルに対する認知・予知・対応能力向上に努めたいと思います。
製造現場において問題は日々発生しているので、私が講義を受講して職場で実施していこうと決めたことは一つ目に、問題発生時の境界線・範囲の差を調査することです。問題が発生するということは予兆が少なくともあるはずで、その予兆も率先して探していこうと考えています。二つ目に、前回はこうだったという考え方は出来る限りしないよう意識することです。講義では広い視野で物事を考える力や、方法を学びました。勉強して終わりではなく実践してからがスタートなので、先ずは小さい問題から実践していきたいと思います。上司への要望としては「原因究明力開発」の講義で今回は班長・班長代行クラスが受講しましたが、中堅クラスからこのような講座を受講することで組織の更なるレベルアップに繋がるように感じました。また、自分はZoomを初めて使用しましたが、少し立ち上げに戸惑ったのでPCに慣れていない交替員を対象にZoomの教育を部内で実施しても良いように思いました。
トラブル事例分析による事故災害の未然防止
普段のKY活動等行っているが、定常作業だと繰り返し行い、マンネリ化していることがあると思う。将棋倒し分析を意識して、さらに安全に作業は出来ないかという思いを持ち、作業する際には安全に作業していく。
事故事例を将棋倒し分析をしたが連絡不足や申し継ぎ不足が多くあり、報連相の重要性を再認識した。自部署で報連相の重要性を再度周知していきたい。
災害を起こさせない為に連鎖のコマを断ち切るよう心掛けていきます。そのために作業前のKYをしっかり行う事が重要であることがわかりました。安全安心な職場を作るために強制劣化の環境を無くすよう現場を改善していきます。
この講義はトラブルプリベンタ(特に協力会社の人に災害を起こさせなくする人)になる事が目的でありました。目的も講義の趣旨は理解したが作業員の私が聞くよりも協力会社と関りのある方が聞くべき講義では?と感じました。自分自身の事故を起こさない為に活かします。
今回の講義で色んなトラブル事例を学習出来て、トラブルを事前に防ぐにはどうするべきか色々考えるいい機会になったので自職場に持ち帰って今後の仕事に活かしていきたいと思います。
将棋倒し分析は、全員が討議をして対策まで考えるので、今後は活用したら良いと思う。新人だけではなくベテランの発表も聞いてみたい。
これまでのトラブル事例でグループ討議を行うことで、様々な意見を受けることが出来たため、今後もグループ討議を他の所で実施していきたい。
現場の化学
化学物質の危険性、有害性とともにそういうものを扱っているという意識を持ち、安全に取り扱うための知識と技術、不安全な状態に不安全だと気づける感性をしっかり身に着けることが大事だと感じました。
計装基礎(対面のみ)
計装分野に関し、今回の講座は非常に役に立ちました。現場ではパネル計器での運転がメインの為、更に踏み込んだ運転条件の設定を同グループの課員と話し合い、設備改善に努めていきたい。
普段使用している計器類については原理などを知る事ができ、より深く理解することができた。また使用したことのない機器、測定器類についても基礎的なことを知ることができた。資料がわかりやすいので実際に使用する時に再度資料を見返して業務に活かしていきたいと思う。
安全・安定運転上級コース(2023年度)
保安防災管理
現場からの視点で、危険を知ることができました。
危険を見つける上で、法的な視点(危険物や可燃性ガスなどの特性)に加えて現場からの視点(装置異常の早期発見)を身につけていきたいと思いました。
各種法令関係も含めて実際の現場で必要な知識が得られたと思う。一部レベルが高い内容もあり、理解が難しいが要点は理解できた。各種ルールを守り、安全な現場で作業を一つ上のレベルで実践したい。
保全管理・技術
今回の講習を通して、製造オペレーターとしての基礎的な知識や業務上で大切なポイントをしっかり学ぶことができた。今回の講習で学んだこと、講師の方が言われたポイントを仕事でも活かしていきたいです。
今回の講習で実習した配管の漏れ処置を実施しなくていいように、外観検査で不具合があるところの修繕を行っていく。また、軍手の使用を禁止し皮手の使用を行っている工場が増えていっているということを知ったので、会社で提言してみようと思います。
課題形成力開発
現場の中核人材になる為、自己啓発で自分のレベルを上げ、同僚に対しリーダーシップを取り、現場をスムーズに動かせるよう、上司、同僚、関係各社とのコミュニケーションをとりたいと思いました。指示のやり方、目的を説明する事が大事と勉強になったので、実際に行おうと思います。目標の3要素を設定し、課題に取り組みます。また効果の確認をしっかりし、反省と今後の展開をしていきます。
部署の課題をいち早く察知するためにもアンテナを高くし、日ごろから現場に足を運ぶことを意識したい。また問題点に気づける力を向上するために、情報や知識をもっと深めていく。5現主義に基づき問題点を明確にして部内に説明し、積極的に部内の問題を改善していく。困りごとがあれば上司に相談しながら確実に進めていく。
今回、課題は何かや解決策など色々なテーマに対してグループディスカッションを行ったが、始めはよく話す人、話さない人に差があり、本当の意味での皆の意見ではなかったように感じた。講義も2日目になり全員が様々な意見を言うようになり、他人の意見に対しても改善できる所を言い合えるようになった。当部署に置き換えて考えた時もまた、意見を言う人、言わない人に差がある。組の雰囲気作りや質問を投げかける等、誰もが意見を言いやすい環境を作るよう努力していきたい。
課題を解決するためにはグループでの話し合いが重要であることを学びました。全員忙しいので、皆を集めて議論する時間を設けることを避けがちですが、実行する前に時間をかけておくことで、実行後の対応に時間が掛からない効果があると感じましたので、一人で検討するのではなく周りを巻き込むこと少しずつ行っていきたいです。
今回の講義では課題を明確化させることの重要さを学びました。明確化するにあたっても全員の意見を聞くことが大切ですし、明確化することによって課題に対しての解決に向かう為のチームの士気が上がることも演習を通じて学ぶことができました。仕事する上では改善活動が大切だと思うので「課題の明確化」を行い、全員で解決していきたいです。
今回学んだ課題形成のポイントや流れ、手段は設計業務においてよく活用できると感じた。まず意識改革という面で「ゼロベース思考」という枠にとらわれない考え方については、設計、施工検討や技術開発課題の検討でしっかりと活用したいと思う。
また今後部署の課題を設計業務(設備投資、技術開発)を通して解決していく必要があると思うが、課題の本質、真の目的は何かということをしっかりと意識した上でチームで課題を解決していきたい。
現業務を行っていく中で、業務の改善を考えていかなければならない機会が増えてきた中で本講義の内容は自分にあっていると感じました。
ブレーンストーミングやPDPC法など今後の改善活動をより効率よくやっていく中で参考にさせていただきたいと感じました。
また、本講義の内容は自分ひとりが身に着けただけでは、充実した活動にはならないと感じましたので、社内に広めて日々有益な討議ができるようにしていきたいです。
現場リーダーの育成
指示の出し方として、「相談型」「説得型」「委任型」「命令型」の4種類がある事を知り、その場に応じた指示の出し方がある事を学べてよかった。命令する事は避けていたが、時には必要という事も念頭において、後輩への指示出しを明確にしていきたいと思う。
コミュニケーションを通し、情報の共有をし、伝達する時には相手に正しく伝わるよう「5W1H」を使い、正確に伝える事を意識する。
仲間と共に職場を活発化させる為に自身が行動することは当然、仲間を巻き込み活動を進めていく。現場リーダーとして技術の継承や新しくなっていく環境に対応し、必然を進め、部下の育成も行っていく。
現場リーダーになるのはまだ先にはなるが、今自分たちを引っ張ってくれている上司の気持ちが少しでも理解できるようになったと思う。なのでリーダーばかりに負担がかからないように、少しでも手伝いができればと思う。
リーダーとなり部下を教育していく際には、作業だけでなく安全意識も一緒に教育していきたい。また、作業を依頼する時には、わかりやすく・責任範囲を説明し出来るだけ自由な環境で行えるようにしていきたい。これからは、リーダーとしての意識を持ち作業をし、安全第一で部下に気を配りながら仕事をしていきたい。
本講義を受けてリーダーに必要な資質を多く学ばせていただきました。部下と接するときは人間性を尊重して人財を大切にする気持ちを忘れないこと。部下の人生を背負う覚悟で部下の為になるコメントを心がけ今後の業務を進めていきたい。
2日間を通して、リーダーをするというのはとても大変なことだと痛感した。怒るのではなく、叱る。放任するのではなく、任せる。この2つの言葉の大きな意味の違いを理解し、後輩と接していきたい。また、優しさだけでは無くある程度厳しさも混ぜていきたいと思った。
今回の講義を通じて以前まで私が思い浮かべていたリーダー像とはかけ離れていた。リーダーとしてメンバーを統一させ目標達成させる為の自身の本質に向き合う機会となった。私には手本となる上司が身近に多いので、あるべくリーダーとして成長したい。安全に妥協する事無く人財育成を行います。
技術力強化コース(2023年度)
改革・改善力開発
今回の講義で感じたことは自分も含めて、左脳(知識、経験、記憶)に頼ってしまっていたことであった。第3者視点や常識を破った考えやアイデアを出すことは難しいが、改善提案や設備投資において維持更新ばかりでなく、視点を変えたアイデアを出していきたい。
問題課題に対して考える事ひとつでも単に考えるのではなく、好奇心を持ちなぜそうなるか考え、持っている知識だけに頼るのではなく冷静に一歩引いてよく全体を把握する事から始め、本当に解決したい物事に対して直感的なヒラメキ発送も取り入れて現場の改善活動に役立ててしっかりと提案・連絡・相談していきたいと思います。また内容を聞いている中で、「自分事」化やKY活動に通じている所も感じたのと、”今後も”継続して活動に取り組んで行きたいと思います。
今回の講義で学ぶことはなかった。作業のみフィードバックは雑、スライドは誤字ばかり、講師の方の話し方も聞き取りにくく、何も伝わってこなかった。この2日間、実際に現場を見てみる方がよっぽど為になると思った。私の上司に対して要望は何もない。ただ山陽人材の方にこの講義の見直しをお願いしたい。このアンケートも上司ではなく、講師か山陽人材の方の手に渡ってほしい。そのくらいひどい内容だった。この講義内容こそ「改革、改善」してみてはどうか。
腐食を考慮したプラントの安全運転
腐食の種類・対策は業務でも特に使用する知識なので、今回の内容をよく復習して理解しておきたい。トラブル時の原因追及は経験も必要だが、知識がないと生き詰まる場面もあるため、腐食に関しては今後も学んでいきたいと思う。
オペレーターとしてのニーズが合わない部分もあったので、少し内容が難しく感じた。腐食防止をプラント運転側として努めたい。特に保温材の点検と熱交換器の流量確認についてはしっかり行いたい。
腐食の起こる原理や要因に対する知識を向上させたことで、設備面では材料の選定や配管レイアウトの検討、運転条件の見直しを図る。また、腐食が起きやすい箇所に対する意識を今まで以上に高め日々のパトロール等で管理強化に努めます。
設備材料の破損と管理
対象を細分化し網羅性を向上させつつ、リスクを考慮しながら関係部署と協議しながら設備管理を実践していく事の重要性がよく理解できました。本講義の内容を活用しながら論理的に事象と向き合っていこうと思います。
今後はこれまで以上にコスト意識を持った設備管理が求められており、これまでの重要度判定で資源配分するような考え方が変わりました。根本的にはPDCAのスパイラルアップ(適切なタイミングでの設備開放)が必要で、様々な検査手法が知れたことは参考になりました。ありがとうございました。
工場内の一般的な事を再確認できた為、勉強になった。製造ラインの中には間違えた選定配管が設置しているかもしれないので立ち会う機会では必ず確認していきたい。
リスクマネジメントコース(2023年度)
- ヒューマンエラーの要因分析と安全推進活動
- 製造設備のリスクマネジメント
- コミュニケーション力開発
- 事故事例から学ぶ化学プラントの防災
- 事故の教訓から学ぶリスクマネジメント
- 仮想体験で学ぶ事故からの教訓(初級)
- 事例から学ぶ労働災害対策
ヒューマンエラーの要因分析と安全推進活動
意図的な不正をなくすことは、工事での安全を確保する上で非常に重要である。今回学んだ、感情を利用してリスクよりも安全を取れるようにしていくという考えを、工事管理に活かしたい。
人間の感情というのは安全設計において不要なものと認識していたが、感情を利用することで有効な安全設計に繋がることがあるということを学べたので、安全対策工事に携わる機会があればこの知識を活かしたい。また、設備の作り手と使い手では視点が異なる為、互いに意見を共有して安全設計を進めていくことが大切だと理解した。
<上司への要望>
仕事でベストパフォーマンスを発揮するには疲労、負担、ストレスが適度な状態であることが必要なので、それを意識して仕事の割り振り・職場の風土作りをお願いします。
一概に自職場に反映できることばかりではないが、かなり有意義な研修だったと思う。適度な作業量やストレス環境を構築することで、さぼらない(指示待ちしない)状態を作り出せると思った。また、ユーザーフレンドリーな現場ではないので、もっと分かり易い表示等を心がける方がヒューマンエラーの防止に繋がる。
疲労の測定等(経時変化による疲労の追跡)を利用し、ポイント化することでエラーが起こりやすい作業を見える化し、現在行ってるしているおせっかいだとか1.5復唱でカバーできるのではないかと思った。ただ、現状運用しているルールが多すぎるため、ルールの添削をまず考える必要があるが。
社会的手抜きにより作業の異常検知率が下がるが、定期的な報連相で情報を共有することで、エラーの可能性を下げれる。
→確りとそういったことを癖付けること(報連相軽視しない)を改めて周知するべき。
年代関係なしに言い合える環境づくりや否定しないというのが重要だと思う。非定常作業では特に必要になると思う。
認知バイアスからリスクとベネフィットの話、フレーミング効果の話は個人的にはすごくタメになると思った。
総じて簡潔にはなるが、ヒューマンエラーの発生要因を表面的に解決することは簡単に見えるが、抜本的に解決するにはいろいろな要因を様々な視点から考慮して考え、速やかに確実に実行しきることが大切であると感じた。しかし素人が考える対策には限界があるのでベースとしてある程度の専門的な知識が必要があると感じた。改めてこういった専門的な視点を持つ方の講習を受けたことで、いろんな考え方や人間の限界や習性を理解することの重要性を学べたので、今後自身の仕事に生かしたい。
事故等のトラブルが発生した際は、人による要素(感情)まで深堀りし、今後の事故防止につながるよう改善できるようにしたい。また、上司の指示であったとしても、リスクがある事象に対しては指摘していきたい。
様々な災害事例を基に表面的でありきたりな対策では、本質的な対策にはなっていない事が良く解かりました。また、講習後では間違いなく危険に対する感度は高くなったと思います。他の人が気づけない「気づき」を社内での安全会議の場で意見したいと思います。
同社でも最近ヒューマンエラーに基づく様々な労働災害が発生しており、様々な対策が行われているが似たような災害が連続している事を感じている。特に思うのが、保護具未装着による労働災害である。
今回の講義で人間工学的な面で、何故人がヒューマンエラーを起こすのか、ルールを守れないのか等、多種のバイアスという言葉で学んだ。
ルールを守れない事について、性善説や精神論ではなくもっと問題点に対し深堀し対策に当たっていく必要を感じた。
製造設備のリスクマネジメント
HAZOPの手法について、演習を通して理解できたので、自プラントや新設設備の設計の際には、リスクマネジメントを実施して、リスク評価を行いたいと思う。
リスクアセスメントを実践できたので良かった。作業員が実施しているので毎日見ているが、実践した事がなかったので勉強になった。現場管理を行っていく上で有意義な時間だった。
コミュニケーション力開発
4つのパーソナルスタイルがあり、様々な考え方や行動の仕方があることを学び、仲間とのコミュニケーションや仕事のやり方をよく考え、今後良い方向に持っていけたら良いなと思いました。すべてのスタイルの人とコミュニケーションを持って仕事をしてみたいと思った。
・職場ではコミュニケーションの必要性がわからない、また苦手な人が増えていると思うので、出来るだけ多くの人に参加してもらいたい。
・それぞれのタイプに合わせた接し方や上手に叱る方法がとても参考になったので、上手に叱っていきたい。また多くの人が上手に叱れるようになれば職場内の雰囲気も少しは明るくなると思う。
上司とはあまりコミュニケーションをとっておらず、どういう人か未だに良く分かっていないので少しずつ分かっていきたいです。
事故事例から学ぶ化学プラントの防災
最新技術導入等が進んできて人がやらなければならない事は今後減っていく。ヒューマンエラーを以下に減らしてくかが重要になってくるので、特に若手社員への教育等で今回学んだ過去トラブルを交えて記憶に残る教育・技術伝承を意識していく。
多くの過去事例から今のKYでよいかもう一回考えることが出来ました。プラントの取り扱い物質についての危険性を再確認したいと思います。
過去の事例を学ぶことの重要性を感じることができましたので、社内で起きている過去の事例に関して学んでいきたい。また、現在も社内での過去の労災や保安事故について学ぶ機会がありますが、そのような機会がもう少し増えてもいいのではないかと感じました。
・変更に対する安全性の評価には設計思想をよく理解しておく必要がある。建設時に構想をまとめ、整理しておくようにする。
・人はミスを犯すという前提で安全対策を考える。
・異常時対応は頻度が少なくパニックになり易いことから自動化を検討する。
事故の教訓から学ぶリスクマネジメント
業務経験が10年弱程度では経験できない事故やトラブル事例があって、今回はその知見を広める良い機会だったと感じる。ここで得た教訓は部下を持ったときや、若手の教育に携わったときだけでなく、日々の工事管理での安全教育や現場周知の際に直結するものだった。know-whyを意識した伝達を心掛け、地道にコツコツと安全を積み上げて事故・災害のない現場づくりを目指す。
化学プラントの電装設備の保全業務に従事し30年ほどになります。これまでも事業所内で大きなトラブルや事故を経験してきました。若い従業員は安全な設備が故、私の経験を伝えていきたいと考えています。過去のトラブルから学んだ工事施工要領など、過去の知見についても、現在の書式に直すなどして、技術伝承として残すことができればと考えています。また、これからも続く定修工事を始め、工事施工管理については、なお一層の安全管理を行っていければと考えています。
今回の教育で、色々な事故事例を映像で視聴し、非常に恐怖を感じました。「安全は絶対に存在しない」ことを念頭に置き、自工場で同じような事故を発生させないよう日々の業務での日常点検を確実に行っていく。又、部下にも「おかしい」「いつもと違う」と感じたらどんな事でも報告するようにし、特に設備が変更された場所については注意を払い、思い込み、勝手判断で絶対に作業しない事を教育していく。工事関係では保全、協力会社と連携が大事だと認識する事ができた。自分もそうだが相手にも怪我をさせないように工事前の安全の作り込みを確実に行い、作業に着手する時にも再確認をする等して受け渡しを行うようにしていきます。これから、自職場に存在する危険源に常に目を向けてトラブルの早期発見で事故を未然に防いでいければと思います。
仮想体験で学ぶ事故からの教訓(初級)
本講座冒頭にて「他山の石」という言葉を考察した。講座内容は、その言葉をまさしく実践する内容だったと捉えている。提示された課題に対し、いかに自分事として落とし込み、その知見を自身の現場の安全につなげていく。
問題の抽出を様々な視点から物事を捉える事ができるため、経験の少ない社員でも有意義な講習であった。今回講義を通じて、故障や事故の展開方法を学ぶ事ができた。一人で故障の問題点を抽出することと複数で抽出するのでは、複数で原因を検討したほうが多くの問題を見つけ、まとめることができると再認識できた。今回の仮想体験としては、他工場の事故など当事者の目線で考え、問題について抽出し、整理・課題抽出する力を鍛えていきたいと思います。また、その方法として、人・設備・技術の三要素を元に該当する点を活用していきたいと思う。
事例から学ぶ労働災害対策
今回の講義で印象に残っている事は、機械、設備の安全装置は正しく使用(作動)出来ているか?という点です。講義中の事故事例でも安全装置はあったが作動しなかった、又は作業性を優先する為、この作業をする時は安全装置を切って作業していたという事例が多かった事です。自部署でも多くの設備に安全装置がついているが毎日作動チェックが出来ているとはいえない場所もある。今後はチェックシートなどを作成し、毎日点検していくようにする。
・安全は、不安全行動、不安全状態を無くす活動だけでは不十分で、ベースとなる安全文化が重要。定期修理のような短期の組織(協力会社含む)で如何に安全文化を醸成するか考え取組んでいきます。
・老朽化したFRPタンクを持っているので、まさか天板に乗るとは思わなかったというケースまで再度安全管理について良く考え業務に反映します。その他、老朽化設備についても検討が必要。
・危険性を伝える時は、できるだけ事故事例も一緒に伝える事に努める。
・防護柵や安全装置は、想定外の人の行動には効果を発揮しない事が多い。こういった死角を理解し残存リスクへの備える事が重要。特にメンテンナンスの時は、これらの安全措置に頼らない対応が必ず必要である事を肝に命じ業務にあたります。
・酸欠はマンホール付近の開けた場所でも起こる可能性がある事を踏まえ作業計画を立てる。
自部場で取り扱っている物質の危険性を知ること、知ってもらう事、ルールを無視するこういう事になる(ケガなど)事を知ってもらいルールを遵守してもらうように安全推進担当として労災が発生しないように取り組んでいく。人の特性も考慮した安全活動を推進していきたい。
競争力強化マネジメントコース(2023年度)
組織とリーダーシップ
現場のリーダーがどのような指示、配置(作業ごとの人員)をしているのか良く聞く。自身も作業の進行状況など、なるべく把握し作業効率をよくする。他の人がどんなタイプの人間か見極め、言葉など選んで指示をする。
指示するだけでなくやって見せるリーダーになりたい。先生面白かったです。内容は難しかった。
自分の考えていたリーダーシップというのが間違っていた。今日の講義を日常の仕事にどう落とし込んでいくかは難しい問題ではあるが、学んだ事を活用していけるようにしたい。全社員に受けて欲しい講義だと思った。
自律型成長人材育成
組織が機能するための3要素、人、ベクトル、プロセスの中で最も土台の 人=人と人との関係性 が重要。上手くいかない組織とは、"縦"、"ブラックBOX体質"で頭と手足のみの関係。自分は実務担当の手足だが、今の立場や役割を理解したうえでそれでも頭と手足を繋ぐ"胴体"になりたいと感じた。one for all、all for oneの捉え方が変わり、衝撃だった。セルフマインド・マネジメントを実践、習慣化して得られる成果を最大化できるように業務に努めたい。所属している他のグループ員にも是非受講してほしい。
自律型成長人材育成講座ということで、どのような事を学ぶか楽しみで参加させて頂きました。様々な内容についてグループディスカッションを行い、自分の意見を伝える事でしっかり考えを纏める事ができました。また様々な意見を聞くことができ勉強になりました。私にグループに管理職の方も居られた為、様々な視点の意見を聞くことができ勉強になりました。今後も他の研修にも参加したいと考えます。宜しくお願い致します。また、永野様、事務局の皆様、2日間お世話になりました。ありがとうございました。
自律型成長人材育成の考え方を小さい事から実践していき、マネジメントできれば横と横の人間関係のつながりが強化され、組織として良い結果になりすべての質が上がると思うので、少しずつ実践振り返りを実践していきます。
メンバーの今の能力をきちんと発揮してもらうための要素として、マインド面が整っているのか、整えるために何ができるのかというアプローチも取り入れる。小さな一歩を繰り返して、適切にフィードバックし、詰まる際には相手の真意を理解してフォロー・再実践するという一連のサイクルを自身も回せるようにしたい。
エネルギー・化学産業と事業連携
カーボンニュートラルに向けた自社のロードマップを作成したい。また、他社との連携が必要なことを理解したので、地域企業の連携協議会などへの入会を勧めたい。
水島コンビナート地区を、客観的に見てどう思われているかという事が非常に良くわかった。その課題をどうしていくか社内でも話し合っていきたいと思う。
社内でも水素やCCSについては各取り組みについて情報が入ってくるが、それはほんとに上っ面の部分が多く、もっと自分から情報を取りに行く必要があるなと感じた。今の仕事も重要だが、20年後を考えると事業は大きく変わっている可能性が高く、先を見据えた勉強を今後していきたい。